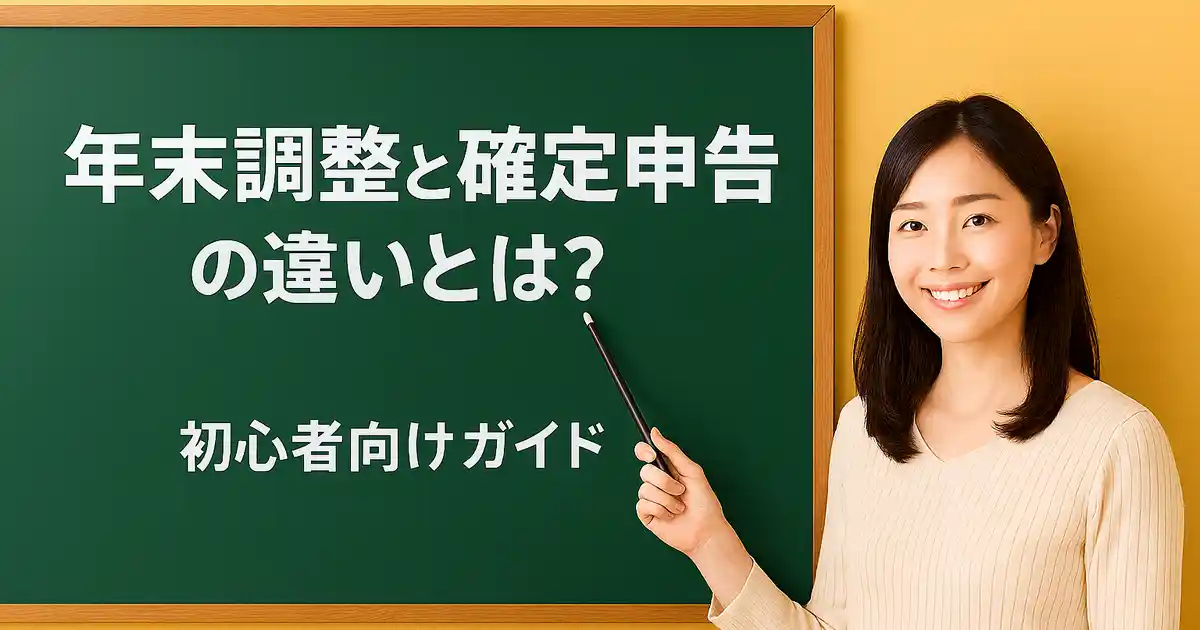「年末調整」と「確定申告」。
どちらも毎年の税金に関わる言葉で、「1年間の所得税を最終的に確定させる手続き」です。
基本的には、会社員やアルバイト、パートなど、会社や個人事業主から給与を受け取っている人は、勤務先で年末調整を受ければ手続きは完了します。
一方で、医療費控除やふるさと納税をした場合、途中入社・退職で年末調整がされなかった場合、アルバイトやパートの掛け持ち、副業収入がある場合などは、追加で「確定申告」が必要になります。
「年末調整をしたから確定申告は不要でしょ?」と思い込んでしまうと、本来受けられるはずの控除や還付を逃したり、追加で申告が必要なケースを見落としてしまうことがあります。
この記事では、
- 年末調整と確定申告の基本的な違い
- それぞれの対象者や時期
- 年末調整でできる控除と、確定申告でしかできない控除
- 会社員やアルバイトでも確定申告が必要になるケース
を整理して、年末調整や確定申告が初めての初心者でも安心して読めるように解説します。
年末調整と確定申告の仕組みの違い
年末調整と確定申告は、どちらも1月1日から12月31日までの「1年間の所得税を最終的に確定させるための手続き」です。
ただし、扱える所得の範囲と、手続きを行う人が異なります。
- 年末調整:会社(勤務先)が従業員に代わって、給与所得の税額を精算する手続き
- 確定申告:納税者本人が、1年間のすべての所得をまとめて税務署に申告する手続き
年末調整の対象は「主たる勤務先の給与所得」に限られます。
一方、確定申告は法律上10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)の所得を対象とし、これらを合算して申告できる総合的な制度です。
もう少し具体的に挙げると、次のような所得もすべて合算して申告します。
- 自営業・フリーランスなどの 事業所得
- アパートや駐車場の賃貸収入などの 不動産所得
- 株式・配当・仮想通貨などの 投資所得や雑所得
- 原稿料・講演料・副業などの 給与以外の収入
つまり、次のような仕組みの違いがあります。
- 年末調整は「会社が給与所得をまとめて精算する制度」
- 確定申告は「納税者がすべての所得を総合的に申告する制度」
知っておきたいポイント
年末調整だけで手続きが完了すると思っている人も多いですが、実際には次のようなケースでは確定申告が必要になります。
- 医療費控除やふるさと納税など、年末調整では反映できない控除がある
- 途中入社や退職で年末調整がされなかった人は、自分で確定申告をしないと精算されない
- 副業収入や掛け持ちバイトがあると、追加の申告が必要になる
といったケースがあり、確定申告は自営業者だけでなく、会社員やアルバイトなどにも関係のある手続きです。
年末調整と確定申告の比較表
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 目的 | 毎月の源泉徴収(概算)と実際の税額の差を精算 | 1年間のすべての所得を集計し、正しい税額を計算 |
| 手続きする人 | 会社(給与の支払者) | 納税者本人 |
| 対象となる所得 | 主たる勤務先の給与所得のみ | 給与・事業・不動産・雑所得などすべて |
| 実施時期 | 毎年12月(最後の給与支給時など) | 翌年2月16日〜3月15日(還付は翌年1月から5年間可能) |
| 主な対象者 | 給与所得者(扶養控除申告書を提出した人) | 自営業・フリーランス、年末調整されなかった給与所得者、控除を追加したい人など |
年末調整でできること(反映できる控除)
年末調整は、給与所得者に関係する控除をまとめて会社が計算してくれる仕組みです。
そのため、ほとんどの会社員やアルバイトは、年末調整を受けるだけで所得税の精算が完了します。
年末調整で適用できる主な控除
| 控除の種類 | 内容 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | すべての納税者に適用される基本の控除 | 給与所得者の基礎控除申告書 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定額以下の場合に適用 | 配偶者控除等申告書 |
| 扶養控除 | 生計を一にする16歳以上の親族がいる場合に適用 | 扶養控除等申告書 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・年金など本人や家族が支払った社会保険料 | 保険料控除申告書、証明書類(国民年金など) |
| 生命保険料控除 | 生命保険・医療保険・個人年金保険の支払額に応じて控除 | 保険料控除申告書、保険料控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の支払額に応じて控除 | 保険料控除申告書、控除証明書 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCoや小規模企業共済の掛金 | 控除証明書 |
| 寡婦控除・ひとり親控除 | 納税者本人が寡婦またはひとり親に該当する場合 | 扶養控除等申告書 |
| 勤労学生控除 | 本人が一定条件の学生の場合 | 扶養控除等申告書など |
| 所得金額調整控除 | 年収850万円超など一定要件を満たす場合 | 基礎控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 |
| 住宅借入金等特別控除(2年目以降) | 住宅ローン控除。初年度は確定申告が必要だが、2年目以降は年末調整で可能 | 控除申告書、年末残高証明書 |
| 特定親族特別控除(令和7年分~) | 所得が一定額の19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合 | 特定親族特別控除申告書 |
年末調整ではできないこと(確定申告が必要な控除)
年末調整で反映できるのは、勤務先が従業員から証明書を集めて確認できる控除が中心です。
逆に、1年間の支出を個人で集計しないと分からない控除や、勤務先が確認できないものは対象外です。
こうした控除を受けるには、自分で確定申告をする必要があります。
具体的には、次のような控除は年末調整では扱えません。
確定申告でなければ適用できない主な控除
| 控除の種類 | 内容 | 確定申告が必要な理由 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 1年間(1/1〜12/31)の医療費が一定額を超えた場合に控除 | 個人ごとに支出額を集計しないと計算できないため |
| セルフメディケーション税制 | 特定の市販薬を1万2千円以上購入した場合に控除(医療費控除と選択適用) | 支出金額を集計する必要があるため |
| 寄附金控除(ふるさと納税含む) | 自治体や公益団体に寄附をした場合に適用 | 寄附の有無・金額を会社では把握できないため |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領などで住宅や家財に損害を受けた場合に控除 | 被害額を個人で計算する必要があるため |
| 住宅借入金等特別控除(初年度) | 住宅ローン控除の最初の年は必ず確定申告 | 初年度は登記書類・借入状況など詳細な確認が必要 |
| 外国税額控除 | 海外で所得税を支払った場合に適用 | 複雑な計算が必要なため |
年末調整を受けているつもりでも確定申告が必要なケース
「勤務先で年末調整をしてくれているから、自分には関係ない」と思いがちですが、実は、給与をもらって働いている人でも、条件によっては確定申告が必要になることがあります。
必要なのに申告していないと、税金を払い過ぎたり、不足分を後から指摘されることもあるため注意が必要です。
確定申告が義務となる主なケース
- 給与収入が2,000万円を超える人
→ この場合は年末調整の対象外となり、自分で確定申告が必要です。 - 副業やアルバイト収入など、給与以外の所得が年間20万円を超える人
→ 雑所得・事業所得・不動産所得などが該当します。 - 2か所以上から給与を受けている人
→ 年末調整されなかった給与や、副業の給与がある場合、合計20万円を超えると確定申告が必要です。 - 年の途中で退職し、その後再就職していない人
→ 退職時点で年末調整が済んでいなければ、自分で申告する必要があります。 - 年末調整に必要な書類を出し忘れた人
→ 扶養控除申告書や保険料控除証明書を提出できなかった場合、反映されない分は確定申告で手続きします。
20万円ルールと注意点
- 従たる給与や副業などの所得が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要とされています(申告不要制度)。
- ただし、住民税の申告は必要です。申告しないと市区町村に収入が正しく伝わらず、後から問い合わせが来る可能性もあります。
- また、副業や掛け持ちの給与は、多くの場合『乙欄(扶養控除申告書を提出できるのは1か所だけのため、その他の勤務先は自動的に乙欄扱いになる)』として扱われ、一律20.42%の税率で源泉徴収されます。
→ この場合、実際の税額より多めに引かれていることが多いため、確定申告をすれば払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
「不要だから申告しない」よりも、「還付を受けるために申告する」方が有利になるケースが多いのがポイントです。
確定申告をすると「得になる」ケース(還付申告)
義務ではなくても、申告することで税金が戻ってくるケースもあります。
- 医療費が多かった
- ふるさと納税をした(ワンストップ特例を使わなかった/使えなかった)
- 保険料やiDeCoの証明書を年末調整に間に合わせられなかった
- 株式や投資の損失を他の所得と通算したい
確定申告は「義務」だけでなく「払いすぎた税金を取り戻すチャンス」でもあります。
まとめ|年末調整と確定申告の違いを正しく理解しよう
年末調整と確定申告は、どちらも「1年間の所得税を確定させるための手続き」です。
ただし、手続きをする人・対象となる所得・扱える控除に違いがあり、自分の状況によって必要な手続きが変わります。
- 最大の違いは「扱える所得の範囲」と「手続きを行う人」
年末調整は勤務先が給与所得をまとめて精算
確定申告は納税者本人が1年間のすべての所得をまとめて申告 - 年末調整でできる控除
扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除・住宅ローン控除(2年目以降)など - 年末調整ではできない控除(確定申告が必要)
医療費控除・ふるさと納税(寄附金控除)・雑損控除・住宅ローン控除の初年度など - 会社員でも確定申告が必要になるケース
給与が2,000万円を超える場合
副業やアルバイト収入など、給与以外の所得が20万円を超える場合
複数勤務先の給与がある場合(20万円以下でも住民税申告は必要)
年の途中で退職して再就職していない場合
年末調整の書類を提出し忘れた場合
年末調整と確定申告は似ているようで違う手続きです。
それぞれの特徴を知っておけば、確定申告が必要なケースや有利になるケースを見落とさずに済みます。
そして、自分にとって必要なことを理解しておけば、税金の手続きを安心して進められるようになります。